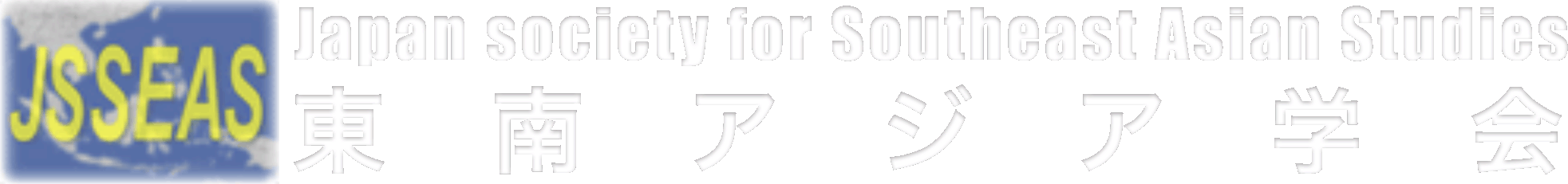東南アジア学会中四国地区例会を「東南アジアの都市における統治性とその変容」というテーマで下記の通り対面のみにて開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。会員以外の方も歓迎します。
【開催日時】2024年10月12日(土)14:00 〜17:30(対面のみ)
14:00~14:50 第一発表
14:50~15: 05 コメント
15:05~15: 35 質疑応答・ディスカッション
(休憩)
15:55~16:45 第二発表
16:45~17:00コメント
17:00~17:30質疑応答・ディスカッション
【会場】広島大学東千田キャンパス未来創生センター3F M304
https://www.hiroshima-u.ac.jp/centers/education_facilities/miraisousei
【プログラム】
第一発表
発表者:藤原尚樹(広島大学大学院人間社会科学研究科 特別研究員PD)
発表題目:「清潔と緑」の都市政治:フィリピン・パシッグ川の都市環境統治性に着目して
要旨:アジアでは1990年代以降、経済成長や中間層の増加に伴って、急速な都市開発が生じてきた。それは建造環境の再編だけでなく、「清潔と緑」の都市空間を希求する都市政治を引き起こした。本報告では、フィリピン・マニラの中心地を流れるパシッグ川の開発プログラムを事例に、河川の環境保全や「清潔と緑」の都市空間へと導く都市環境統治性の政治を考察する。パシッグ川は、全長24キロメートルを有するマニラの主要河川であるが、60年代から70年代にかけて川沿いの非正規住居や工場の増加によって環境汚染の問題が生じた。1970年代のマルコス政権時から開発計画が構想されたものの具現化しなかったが、ラモス政権が1993年に開始した「パシッグ川再生プログラム」はパシッグ川の開発の萌芽となり、2008年まで継続した。本報告は、同プログラムとパシッグ川が流れるマカティ市の都市緑地化プログラムに焦点を当てて、民主主義社会のもとでどのように「清潔と緑」の都市政治が台頭し、パシッグ川沿いの空間再編と都市貧困層の立ち退きとが生じたのかを考察する。
コメンテーター:太田和宏(神戸大学)
第二発表
発表者:久納源太(京都大学 東南アジア地域研究研究所 機関研究員)
発表題目:監視カメラに見るジャカルタにおける監視の複合性
発表要旨:インドネシア都市部では、自警団や義賊、地域警察活動や民兵団が、秩序維持・社会制御の担い手として存続し、植民地期の間接統治を受け継ぐ新自由主義的な都市統治の形態となっている(Kusno 2007; Barker 2024)。こうした国家・共同体の監視が複合する監視社会は、少なくとも権威主義体制の安定期である1980年代に確立したが、民主化やデジタル化を経た2000年代中盤から急速に変化してきた。本発表では、インドネシア最大の都市ジャカルタを対象に、統計解析と事例研究を通して、監視カメラの普及がもたらした監視社会の変化を明らかにする。まず、「伝統的な」自警団が監視カメラを採用する事例として、地方予算を用いた住民組織による監視カメラの採用を取り挙げ、政府に支援された監視カメラの供給が過密地域へ監視カメラを浸透させてきたことを整理する。次に、中間・富裕層に仕える監視カメラがリスクを監視するだけでなく、共同体の監視・紐帯自体を監視していることを検討する。監視カメラは、一方で国家・共同体の監視を拡張するものとして、他方でそうした複合的監視から逃れる個人を担保する監視の実践として普及してきた。さらに、その特徴として、前者が貧困・過密地域に、後者が中間・富裕層に集中するパターンが形成されている。終わりに、以上の現代ジャカルタの監視の複合性の特徴を踏まえ、今後の展望について議論する。
Barker, J. (2024). State of Fear: Policing a Postcolonial City. Duke University Press.
Kusno, A. (2007). Gardu penjaga memori. Ombak.
コメンテーター:吉田航太(静岡県立大学)