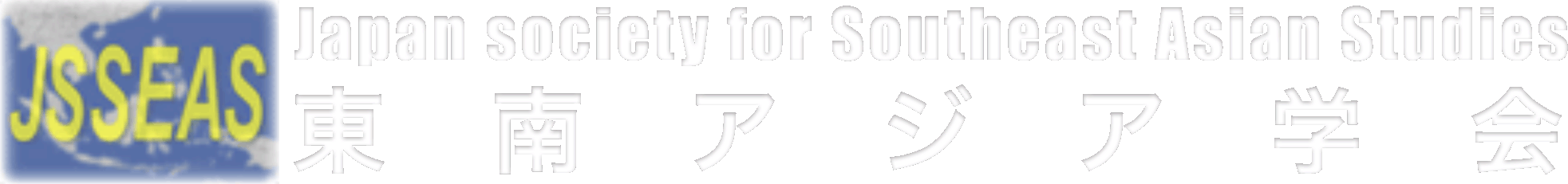東南アジア学会6月関西例会を次の通り開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。会員以外の方も歓迎します。
参加希望の方は下記の登録フォームからお申込みください。
【日時】2024年6月29日(土)14:00~16:10
14:00~15:00 第一発表
15:00~15:10 コメント
15:10~16:10 質疑応答・ディスカッション
【会場】京都大学吉田本部キャンパス 総合研究2号館4階 第1講義室(AA401)
【登録フォーム】
① 対面
https://forms.gle/jqVsAV5DrLqv3MSMA
② ZOOM
このミーティングに事前登録する:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuutrTorHdcBiyJuFeDSo2kdz7gyiS9V
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
*Zoom参加の場合、登録後、登録メールアドレス宛にミーティング情報が届きます。
【プログラム】
発表者:大橋厚子・柳澤雅之(京都大学東南アジア地域研究研究所)(共同発表)
発表題目:東南アジアの中央政権と地域住民の間:歴史学と歴史人類学の協力、およびツール紹介
コメンテーター:片岡樹(京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科)
発表要旨:
中国やインドのような巨大な国家の地域社会と比べると、近現代史において、東南アジア各国の地域社会では国家の影響がより近接している場合が多い。東南アジアでは、19世紀後半から20世紀初めに「制度化された行政機構と村落を通じて国家が農民を組織的に支配する仕組みが(中略)広がっていった。」(加納 2001:307)と言われ、さらに主要国は独立後開発独裁下で工業化を開始する。
しかし中央政府と地域社会の関係の動態を把握するのは容易ではない。たとえば発表者が専門とするインドネシア史では先行研究としてまず白石隆の植民地官僚制・スハルト期の官僚制に関する秀逸な論考が想起されるが、概説の形をとり地域差には言及がない。他方、近年日本で歴史人類学の進展が著しい。そこで人類学と歴史学の互いの強みを生かしてこの中央と地域社会の関係に近接したいと考える。本発表では歴史学からの手始めの方法として輸送・交通の遠近難易に焦点を当てる例を示す。この分野を取り上げるのは開発独裁下、一次産品を大量に輸出しながら緑の革命と工業化を開始した各国にとって国内の物流網の在り方はクリティカルだったと考えられるためである。
事例としてインドネシア・南スラウェシ州中南部などの1、2の地域を取り上げ、先行研究と公刊史料を整理しながら人類学と歴史学の協力方法を探る。協力のツールとしてフィールドノート・アーカイブを紹介したい。ただし発表者2名が一番伝えたいのは、異なるディシプリンの地域研者が地図を見ながら情報交換することは実りが大きくかつ楽しいこと、にある。その地図が伸縮移動自在の世界地図であればなおさらである。
【お問合せ】y.sugahara.hmt[at mark]osaka-u.ac.jp
東南アジア学会関西理事 菅原由美