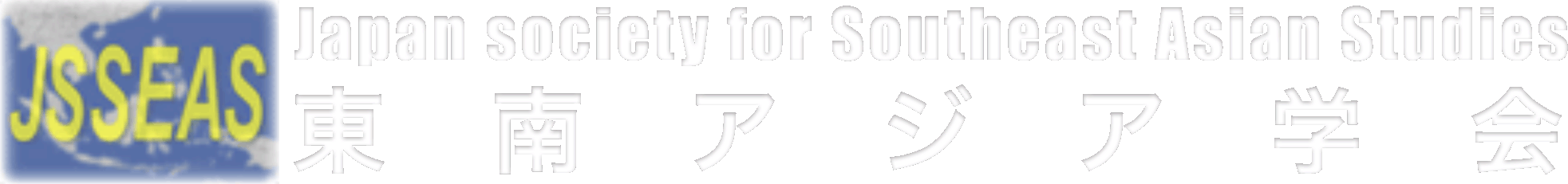東南アジア学会員のみなさま
広島大学の関恒樹と申します。以下の通り、東南アジア学会中四国地区例会を開催いたします。事前登録などの必要はありません。みなさまのご参加をお待ちしております。会員以外の方のご参加も歓迎いたします。
【開催日時】2024年10月19日(日)14:00 〜17:30(対面のみ)
14:00~14:50 第一発表
14:50~15: 05 コメント
15:05~15: 35 質疑応答・ディスカッション
(休憩)
15:55~16:45 第二発表
16:45~17:00コメント
17:00~17:30質疑応答・ディスカッション
【会場】広島大学東千田キャンパス未来創生センター3F M302
https://www.hiroshima-u.ac.jp/centers/education_facilities/miraisousei
【プログラム】
第一発表
発表者:河野佳春(弓削商船高等専門学校)
発表題目:インドネシアにおける歴史的津波と災害対応の「伝統知」―中マルク地域を中心に―
要旨:2004年スマトラ島沖地震津波を契機に、インドネシアでは津波災害に対する関心が高まり、「伝統知」の再評価が進んだ。本報告は、それを踏まえて、報告者の主たる関心対象地域である中マルク(マルク諸島中央部)を中心に、歴史的津波災害事例と村落の防災・減災にかかわる「伝統知」を紹介し、考察を加える。特に、(1)1674年アンボン津波、(2)1899年エルパプティ津波、(3)1950年アンボン津波を詳しく取り上げる。(1)と(2)は地震直後に巨大な津波が襲い、大きな被害が発生した。防災の余地はほとんどなかったように見えるが、それでも居住地の選定や避難などの「伝統知」に一定の効果が認められる。対して(3)は、(1)(2)に比べて津波の規模や襲来までの時間において好条件であったとはいえ、「伝統知」によって被害が極限に抑えられた事例である。南マルク共和国反乱という政治的混乱の最中であり、また住民には津波の知識がなかったにもかかわらず、森林や高地という既定の場所に避難する行動が、人的被害を最小限に抑えた。
もちろん「伝統知」は確定的な知識ではなく、歴史的に変化し続けている。現在も2004年以降の津波に関する注目と科学的知識の普及、政策の発展と相まって、村落社会生活において変化している。残念ながら、具体的な変遷を史料的に明らかにすることはできない。そこでここでは現在の人々の歴史認識を通じて考察する。
コメンテーター:中野真備(甲南女子大学)
第二発表
発表者:西尾善太(愛媛大学)
発表題目:都市概念再考ーマニラとジープニーの事例から
発表要旨:本発表は、自著『人間の都市:マニラを鼓動させるジープニーとおっちゃん』で提起した問題意識を発展させ、都市概念の脱植民地的再考を試みるものである。近年の批判地理学、とりわけ惑星都市理論は、都市化を高密度空間に限定せず、後背地や資源循環をも含む広範な社会=空間の再編過程として捉え直した。しかし、そこに潜む都市概念は依然として西欧的な歴史経験と人間像を基盤にしており、非西欧的都市の経験を周縁化しがちである。
本発表は、都市化を「単一の普遍過程」ではなく「異なる人間像の対立と協働が織りなす歴史的プロセス」として捉える視座を提示する。その具体例として、フィリピン・マニラ首都圏における公共交通機関ジープニーと、その運行・管理を担う人々の歴史的軌跡、日常実践、政治的闘争を取り上げる。ジープニーをめぐる技術・労働・規制の絡み合いを都市の形成過程と位置づけることで、西欧中心に序列化されてきた都市概念を問い直し、都市を複数的・関係的な生成過程として描き出すことを目指す。
コメンテーター:青木秀男(社会理論・動態研究所)
【お問合せ】関恒樹(seki[atmark]hiroshima-u.ac.jp) またはreikai31-sea[atmark]ml.rikkyo.ac.jp
東南アジア学会地区担当理事
小座野八光、佐久間香子、篠崎香織、菅原由美、関恒樹、丸井雅子