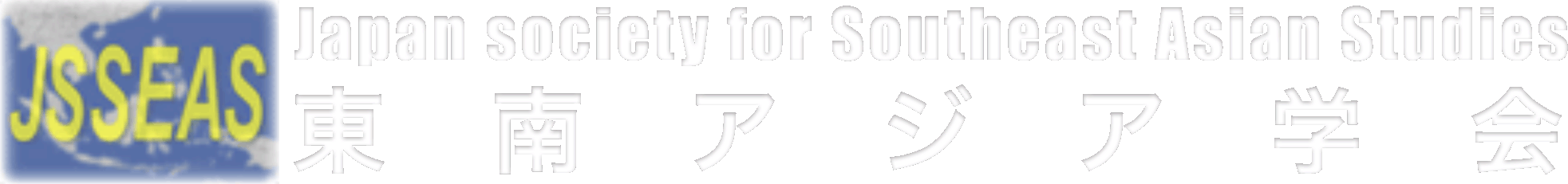このたび、下記の通り、科研費「東南アジア古代宗教世界における「コトバとモノの関係史」への地域横断的アプローチ」(基盤B/研究代表者:佐藤桂)のオンライン研究会を開催いたします。
今回は、本年8月に実施したインド調査に基づき、青山亨先生からご発表いただきます。
ぜひご参加いただき、活発な意見交換の場としてくだされば幸いです。
*****
日 時:2024年11月24日(日) 13:00-14:30(Zoom開催。情報担当注記:Zoom IDは寺井淳一会員にお問い合わせください)
発表者:青山亨(東京外国語大学名誉教授)
タイトル:アジャンター第17石窟に見られる「スタソーマ本生物語」について:斑足王とスタソーマの物語が交わるところ
概 要:アジャンター石窟群の中でも第17石窟はジャータカ(本生物語)をモチーフとする壁画が最も多く残されていることで知られる。刻文によると石窟はヴァーカータカ朝のハリセーナ王(475~500年頃)在世期の建立と推定されている。石窟に見られるジャータカの1つがMahā-Sutasoma Jātaka(スタソーマ本生物語)である。しかしながら、今年の現地調査で実見したところ、壁画の内容はパーリ語仏典の『ジャータカ』に収録されているMahā-Sutasoma Jātaka(no. 537)とは異なっており、むしろKalmāṣapāda(斑足王)の物語とよく一致することが判明した。斑足王の物語は広義の「スタソーマ物語群」の一部を成すものであるが、スタソーマの物語とは本来、系統を異にすると考えられている。一方、東南アジアではジャワ島中部のボロブドゥール寺院(9世紀)の浮彫に「スタソーマ本生物語」が描かれているが、これはサンスクリット語仏教物語集『ジャータカ・マーラー』を出典としており、斑足王の要素は見られない。しかし、14世紀にジャワ島東部で成立した古ジャワ語叙事詩『スタソーマ・カカウィン』には、スタソーマの物語の要素を主としつつも、斑足王の物語の要素が断片的ではあるが含まれている。報告者はこれまで『スタソーマ・カカウィン』における斑足王の物語の要素はパーリ仏典の影響と推測していたが、アジャンター石窟の壁画は、パーリ語仏典の『ジャータカ』が成立する前に、インドにおいて斑足王の物語とスタソーマの物語が交錯する形の物語が流通していたことを示しており、このような形の「スタソーマ本生物語」がジャワにも流入していた可能性を検討する必要があると考えるに至った。
*****
多くの方々のご参加をお待ちしております。
質問等がございましたら、寺井宛てにご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
寺井 淳一
国立民族学博物館・外来研究員
terazaemon[atmark]gmail.com