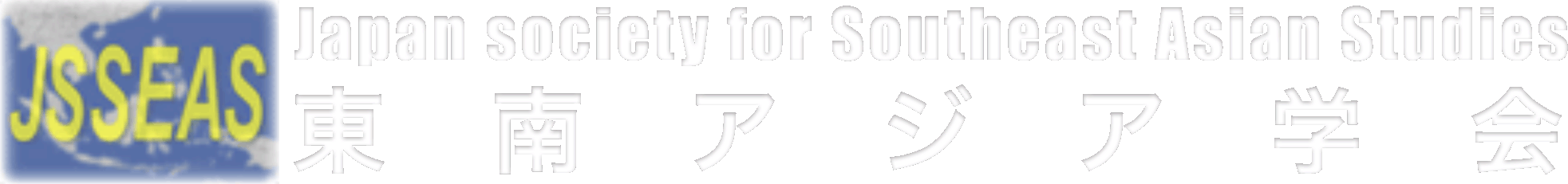下記の通り「白山人類学研究会」
本研究会は、人間文化研究機構海域アジア・オセアニア研究(
ショートノーティスで恐縮ですが、
Zoomを使用したオンラインと対面とのハイフレックス方式にて
ショートノーティスで恐縮ですが、
Zoomを使用したオンラインと対面とのハイフレックス方式にて
参加ご希望の方は以下のフォームからご登録ください。
アクセス用のリンクについては、
https://forms.gle/
開始の5~10分前にログインしてください。
アクセス用のリンクについては、
https://forms.gle/
開始の5~10分前にログインしてください。
□発表題目
船大工のクラフツマンシップ-インドネシア・
□発表者
明星つきこ(日本学術振興会・東洋大学)
□要旨
インドネシア・南スラウェシ州コンジョ地域は、ピニシ船(
本研究では、人類学的参与観察をもとに、
本研究では、人類学的参与観察をもとに、
++++白山人類学研究会+++++
112-8606 東京都文京区白山5-28-20
東洋大学社会学部長津一史研究室内
白山人類学研究会
hakusanjinrui[at mark]gmail.com
112-8606 東京都文京区白山5-28-20
東洋大学社会学部長津一史研究室内
白山人類学研究会
hakusanjinrui[at mark]gmail.com