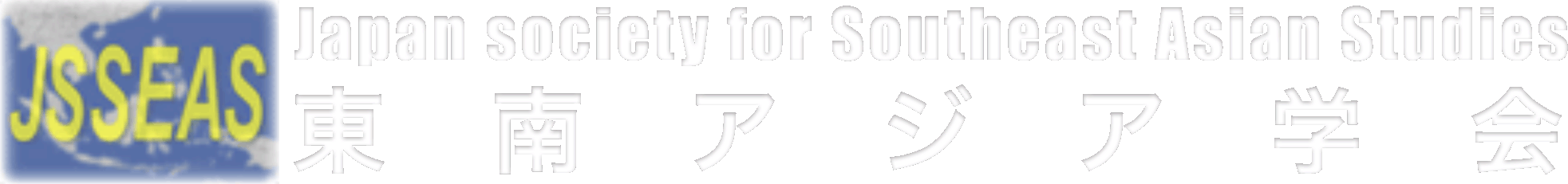The Japan Society for Southeast Asian Studies (JSSEAS or Tōnan Ajia Gakkai in Japanese) was established in November 1966 to promote the study of the history, cultures, languages and societies of Southeast Asia in Japan under the name of JSSAH or Tōnan Ajia Shi Gakkai. The present membership amounts to more than 750 (as of December 2015), including historians, archaeologists, anthropologists, linguists and other social scientists.
Latest News
-
都市研究関連・新刊本の合評会(7月20日)
東南アジア学会員の皆様、 下記の通り、都市研究関連の新刊2冊の著者をお呼びし、合評会を開催します。ご関心あれば、是非ご参加ください(会場の建物がオートロックのため、末尾の注意事項をご確認下さい)。 日時:7月20日(日)14:00~17:00 (開催形式:対面) 報告①:西尾善太(愛媛大学) 『人間の都市:マニラを鼓動させるジープニーとおっちゃん』(花伝社) https://www.kadensha.net/book/b10132113.html 評者:石岡丈昇(日本大学) 報告②:内田奈芳美(埼玉大学) 『ネイバーフッド都市シアトル:リベラルな市民と資本が変えた街』(学芸出版社) https://gakugei-pub-plus.stores.jp/items/6837e27a00d7d549215586ee 評者:任哲(アジア経済研究所) 会場:早稲田大学大学院アジア太平洋研究科(早稲田キャンパス19号館)710教室 https://www.waseda.jp/fire/gsaps/access (アクセス) *要注意:日曜日のため、19号館の正面玄関の開錠は、13:40―14:30のみとなります。 遅れて参加する予定の方は、遠藤(tendo[atmark]waseda.jp)まで事前にご連絡下さい。 主催:科研研究「都市インフォーマリティと新しい社会契約(25H00518)」、グローバルサウスの都市論研究会、アジアの都市における経済社会研究部会(GSAPS)の共催 遠藤環 -
山田勇さんをしのぶ会
山田勇さんと学びを分かちあった方々へ 拝啓 京都では祇園祭が宵山の夜を迎えようとしています。皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。すでにご承知のことと存じますが、東南アジアをはじめとする熱帯林の研究に多大なご貢献をなされた京都大学名誉教授・山田勇さんが本年6月9日にご逝去されました。 このたび、山田勇さんを偲び、在りし日の思い出やご功績を語りあいながら、故人の魅力にあふれた生き様をともに振り返る機会として、有志により「しのぶ会」を下記のとおり開催する運びとなりました。当日の詳細につきましては改めてご案内いたしますが、まずは第1報として、開催日時と場所をお知らせ申し上げます。ご多忙とは存じますが、まずは下記、ご予定いただければ幸いです。 ■ 名称(仮): 山田勇さんをしのぶ会 ■ 日時: 2025年10月18日(土) 第1部:山田勇さんの思い出を語る 14:00~16:00(予定) ※無料:どなたでもご参加いただけます。 第2部:仲間・教え子の懇談会 17:00~19:30(予定) ※会費制とする予定です。ご香典・ご供花等は固くご遠慮申し上げます。 ■ 会場: 京都大学東南アジア地域研究研究所 稲盛記念館 なお、当日は平服でお気軽にご参加ください。 発起人(五十音順・敬称略): 赤嶺淳、東桂、阿部健一、安藤和雄、飯塚宜子、伊谷樹一、市川昌広、及川洋征、岡本正明、落合雪野、加賀道、加川真美、片岡稔子、神崎護、甲山治、河野泰之、小坂康之、小林知、島上宗子、鈴木伸二、園江満、竹田晋也、内藤大輔、長津一史、西本希呼、畑正高、平田昌弘、三重野文晴、柳澤雅之 お問い合わせ先: 市川昌広(高知大学) Email:ichikawam[at mark]kochi-u.ac.jp 山田さんを敬愛された皆様とともに、そのご遺徳を偲び、語り合えるひとときを持てればと願っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 敬具 【呼びかけ人事務局】阿部健一、飯塚宜子、市川昌広(代表)、内藤大輔、長津一史、柳澤雅之 -
高校生探究成果発表会+関西例会特別企画のお知らせ
東南アジア学会の皆様 以下の通り、7月26日に阪大箕面キャンパスにて、「東南アジアと戦後80年」をテーマに、2つのプログラムを実施します。午前は対面のみ、午後(関西例会)はハイブリットで行います。皆様のご参加をお待ちしています。 菅原由美(東南アジア学会 教育・社会連携委員) 阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025高校生探究成果発表会 日時:2025年7月26日(土)10:00~12:00 場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top 開催形態:対面のみ 10:00〜12:00 高校生発表(10分発表 10分コメント) 10:05~10:25 インドネシア 「歴史教科書に書かれた日本占領期」 10:25~10:45 フィリピン 「記憶の想起と忘却:マニラ市街戦」 10:45~11:05 タイ 「戦前〜戦中期の同時代資料『暹羅協会々報』を読む」 11:05~11:25 ビルマ「泰緬鉄道の記憶と記録」 11:25~11:45 ベトナム「ベトナム残留日本兵」 11:45~ 全体講評 参加賞授与 12:00~13:00 休憩 @5F学生交流スペース 応募締め切り 7月24日17:00 登録フォーム(対面) https://forms.gle/37L1Q76QBrUyvgySA 参加条件:発表者関係者、高校生、高校教員、大学生、大学教員、その他教育関係者 連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp 共催: 東南アジア学会 教育・社会連携、関西例会 東南アジア学会関西例会特別企画 一般公開シンポジウム 「日本占領期の記録と記憶-東南アジアと戦後80年」 日時:2025年7月26日(土)13:00~17:00 場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10 北大阪急行線 箕面船場阪大前駅下車 徒歩 約3分 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top 開催形態:対面を重視したハイフレックス形式 趣旨: 今年(2025年)は第二次世界大戦終結後80年となりますが、近年、戦争経験を持つ世代が数少なくなり、東南アジアの日本占領もかつてほど研究テーマとして取り上げられなくなってきています。では、東南アジア各国は現在の東南アジア各国建国の契機となった「あの戦争」をどのように記憶する(または記憶しない)選択をしたのでしょうか。本イベントは80年という時間の経過のなかで彼らが作り上げた「歴史」とはどのようなものであるかを議論する場としたいと考えています。 スピーカー: 柿崎一郎(横浜市立大学国際教養学部) 岡田泰平(東京大学大学院総合文化研究科) 池田一人(大阪大学大学院人文学研究科) 師田史子(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科) 12:30 開場 13:00~13:05 趣旨 13:10~14:00 柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係」 14:05~14:55 岡田泰平「「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」 15:10~16:00 池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録―ビルマ人の場合」 16:05~16:55 師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」 ★ 午前中(10:00~12:00)は、「阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025:東南アジアと戦後80年」の高校生による成果発表がおこなわれます。 応募締め切り 7月24日17:00 登録フォーム(対面) https://forms.gle/XXaN5coJ5D5GAD1T6 登録フォーム(オンライン) https://us02web.zoom.us/meeting/register/jPRaHTWxQGmGgFVvqJi-8Q 連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp 要旨: 柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係―」 タイは開戦当初に日本軍と同盟を結んで枢軸国側に立つことを決意したが、枢軸国側の戦況悪化に伴い、日本との同盟を決意したピブーン首相も日本との距離を取り始める。他方で、タイ国内外で抗日を模索していたグループが連携し、連合国側と協力して抗日蜂起を模索した。この「自由タイ運動」の首謀者であった摂政プリーディーが、日本軍の降伏受諾後直ちに連合軍側への宣戦布告を無効とする「平和宣言」を発表し、「敗戦国」としての扱いを逃れようと画策した。このため、タイにおける第2次世界大戦観は「自由タイ運動」を重視したものであり、日本との同盟の歴史を「負の遺産」と見なすものである。これに対し、当時日本側との連絡役を担っていた職員が作成した同時代資料からは、タイと日本の関係が対等ではなかった点への不満や、自らが日本軍の「手先」と見なされることへの憂慮を読み取ることができ、日タイ同盟の実像の一端を垣間見ることができる。 岡田泰平「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」 この発表では、まずはフィリピン戦における実相を論じ、その上で日比双方の「戦記もの」を読み解いていくことにより、戦争の実相がどのように日比の記憶の中に位置づけられていったのかを確認したい。時が経つにつれて、戦争の記憶は変質していく。1970年代、1980年代になると、すでに時間的にも地理的にも遠くなったフィリピン戦をどのように評価するのかという問題がある一方、フィリピンに慰霊に行く日本人が多くなる。そのような中で、新たな日比の関係が築かれていく。たしかに、フィリピン人の「厚意」(許し)と日本人の「お詫び」という好循環が生じてくるのだが、他方では、新たな日比間の関係を築けない事例も多かった。この発表では、幾つかの事例から、凄惨な経験から生じるものの帰結や同意に達しない関係、つまり「宙ぶらりんの関係」を紹介する。歴史教育の一環として、そしてまた地域研究にとって、そのような「宙ぶらりんな関係」が持つ意義を考えてみたい。 池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録:ビルマ人の場合」 泰緬鉄道は、1943年10月に日本軍がタイ=ビルマ(ミャンマー)間に開通させた軍需物資の輸送鉄道だ。わずか1年4ヶ月の突貫工事で密林地帯を走る415キロを完工できたのは、62,000人の連合軍捕虜と20万を超えるとされる現地労務者の酷使と犠牲があったからであった。戦後、泰緬鉄道の建設が日本軍によるジュネーブ条約に反する戦争犯罪としてひろく世界に知られるようになったが、それは1957年のハリウッド映画「戦場にかける橋」の世界興行と、元捕虜による告発が数多くなされたことによる。日本側では反発とともに永瀬隆氏による贖罪活動が行われた。彼の活動は英蘭豪米の元捕虜との交流と和解の活動にもつながった。こうして「泰緬鉄道」は、日本と欧米において第二次世界大戦史の重要な記憶と記録として定着した。では、現地の人々にとって、それはどのような出来事として記憶され記録されているのだろうか。とくにビルマ人にとっての戦後(独立後)の「泰緬鉄道」を考えてみたい。 師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」 戦後80年を迎えた今も、山下財宝伝説はフィリピン社会に色あせることなく息づく。山下財宝とは、山下奉文大将率いる第十四方面軍がフィリピンに埋めたとされるアジア各国の金銀財宝のことを指す。人々の日常の語りや実践において財宝は、地中に埋もれた遺物として想像されると同時に、未来への可能性を託す地下資源としてもイメージされる。土地に堆積した過去は生活世界の折々に表面化し、財宝の潜在的存在を浮かび上がらせるとともに「あの戦争」や「あの時の日本人」の記憶を確かに呼び起こす。本発表では、こうして反復生成される山下財宝伝説を通じて、正史として記録に残ることのない、残渣としての戦争記憶をいかに人々が共同的・社会的に紡ぎ続けているのかを検討する。 PDF版ポスターはこちら -
教員公募(立命館アジア太平洋大学)
東南アジア学会の皆様: 立命館アジア太平洋大学の蓮田です。現在、本学にて地域研究の公募を行っております。会員の方々あるいはお知り合いの方々に適任の方がおられましたら、応募の検討並びにご案内をお願いします。 ・JREC-IN PortalからWEB応募です。 ・締切は本年7月15日23:59(日本時間) ・推薦状2通が必要ですが、それについては推薦者より直接所定のメールアドレスにお送りいただくことになります。 その他、詳細は下記リンクならびに本学の採用情報ページ(https://www.apu.ac.jp/home/contents/jobs.html/)をご参照ください。 JREC-IN応募ページ:https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?&id=D125050360 -
保護中: 会報122号ダウンロードページ
会報122号は、ここからダウンロードできます。
-
「ジェームス・スコットの生涯・思想・世界 追悼研究会」
東南アジア学会会員の皆様 神戸大学の下條尚志です。 下記のとおり、研究会のご案内をいたします。 奮ってご参加ください。 https://www.kasasustainability.org/workshop ジェームス・スコットの生涯・思想・世界 追悼研究会 日時:2025年7月19日(土)10時〜16時 会場:上智大学 10号館 301・ZOOM(ハイブリット形式) 参加申し込み:下記のURL先、QRコードから事前登録 https://www.kasasustainability.org/event-details/james-scott-event 共催:東南アジア学会 プログラム 1. 今村真央(山形大学) 「言語と王権: スコット対ポロック」 2. 片岡樹(京都大学) 「スコットの宗教論」 3. 日下渉(東京外国語大学) 「スコットと政治学」 4. 麻田玲(山口大学) 「スコットと農村の生存戦略」 5. 下條尚志(神戸大学) 「スコットのモラル論再考」 6. 石川登(京都大学) 「ゾミア論のアップデート: :スコットさんからバトンを受けて」 7. シンワ・ノー(上智大学)From State Evasion to Aspiring State-Making: Political Evolution... -
「恩師が導いてくれたアジアへの道」オンライン開催(8/6 12:15- )
東南アジア学会のみなさま こんにちは。東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(U-PARL)・特任研究員(東南アジア担当)の田中です。 U-PARLは、(東南)アジア研究者の裾野を広げるべく、2025年8月5・6日にオンライン開催される、東京大学オープンキャンパスで以下の企画を準備しています。 高校生以外の方でもご覧いただけます。周囲の方々にもぜひお声掛けいただきますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 *ご参加には、東京大学オープンキャンパスウェブサイトでのお申込みが必要です。 https://sites.google.com/view/utokyo-opencampus =============== アジアンライブラリーカフェNo.010「恩師が導いてくれたアジアへの道」 https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/japanese/opencampus2025#asianlibrarycafe10 日時:8月6日(水) 12:15ー13:45 定員:250名(先着順) 講演者:鴨下顕彦(農学生命科学研究科 附属アジア生物資源環境研究センター) オーストラリアに留学、その後、フィリピンの国際稲研究所でポスト・ドクター。タイなどの天水田地域で、収量をどうしたら増やせるかの課題に取り組み、さらに、インドとカンボジアにもプロジェクトを拡大した経歴を持つ。 司会:志水正敏(農学生命科学研究科 One Earth Guardians 育成機構) 今回のアジアンライブラリーカフェでは、鴨下先生が大学の農学部で出会った恩師、日本の農学者:石井龍一先生との出会いについて語っていただきます。そして、鴨下先生ご自身がどうして日本の外のアジアの国々と学術交流をするようになったのか、さらには農学や生物資源環境学という分野が、課題と共に魅力を持った分野だということを、お話しいただきます。鴨下先生が集められた、カンボジアの子供たちが描いた農村の風景もご紹介します。 【鴨下先生からの言葉】 「(オープンキャンパス当日の)8月6日は、広島に原爆が投下されて80年を記憶する日です。なぜ記憶するか、それは、歴史の中でかつて起きた出来事が、いまの私たちの世の中の状態に影響を残しているからです。今後私たちがどういう選択をして生きてゆくべきなのか、示唆を与えるからです。歴史的な出来事が、今の私たちに言葉を語りかけているように、私たちがかつて出会った人も、私たちに言葉を語りかけているのだと思います。」 鴨下先生についてもっとよく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。 → 【アジア研究多士済々】鴨下 顕彦 先生(アジア生物資源環境研究センター)2017年10月 =============== みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げております。 田中あき -
アビナレス教授によるマルコス政権期のフィリピン大学研究所PCASに関する研究発表
2025年8月1日、アビナレスさん(京都大学東南アジア地域研究研究所招へい研究員) にマルコス政権期にフィリピン大学に設置されたシンクタンク兼研究組織のPCAS について発表していただきます。高木佑輔さんにコメントをしてもらいます。 詳細は下記のURLでご確認ください。ご参加お待ちしています。 https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/event/20250801/ -
高校生探究成果発表会+関西例会特別企画のお知らせ
東南アジア学会の皆様 以下の通り、7月26日に阪大箕面キャンパスにて、「東南アジアと戦後80年」をテーマに、2つのプログラムを実施します。午前は対面のみ、午後(関西例会)はハイブリットで行います。皆様のご参加をお待ちしています。 菅原由美(東南アジア学会 教育・社会連携委員) 阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025高校生探究成果発表会 日時:2025年7月26日(土)10:00~12:00 場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top 開催形態:対面のみ 10:00〜12:00 高校生発表(10分発表 10分コメント) 10:05~10:25 インドネシア 「歴史教科書に書かれた日本占領期」 10:25~10:45 フィリピン 「記憶の想起と忘却:マニラ市街戦」 10:45~11:05 タイ 「戦前〜戦中期の同時代資料『暹羅協会々報』を読む」 11:05~11:25 ビルマ「泰緬鉄道の記憶と記録」 11:25~11:45 ベトナム「ベトナム残留日本兵」 11:45~ 全体講評 参加賞授与 12:00~13:00 休憩 @5F学生交流スペース 応募締め切り 7月24日17:00 登録フォーム(対面) https://forms.gle/37L1Q76QBrUyvgySA 参加条件:発表者関係者、高校生、高校教員、大学生、大学教員、その他教育関係者 連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp 共催: 東南アジア学会 教育・社会連携、関西例会 東南アジア学会関西例会特別企画 一般公開シンポジウム 「日本占領期の記録と記憶-東南アジアと戦後80年」 日時:2025年7月26日(土)13:00~17:00 場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10 北大阪急行線 箕面船場阪大前駅下車 徒歩 約3分 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top 開催形態:対面を重視したハイフレックス形式 趣旨: 今年(2025年)は第二次世界大戦終結後80年となりますが、近年、戦争経験を持つ世代が数少なくなり、東南アジアの日本占領もかつてほど研究テーマとして取り上げられなくなってきています。では、東南アジア各国は現在の東南アジア各国建国の契機となった「あの戦争」をどのように記憶する(または記憶しない)選択をしたのでしょうか。本イベントは80年という時間の経過のなかで彼らが作り上げた「歴史」とはどのようなものであるかを議論する場としたいと考えています。 スピーカー: 柿崎一郎(横浜市立大学国際教養学部) 岡田泰平(東京大学大学院総合文化研究科) 池田一人(大阪大学大学院人文学研究科) 師田史子(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科) 12:30 開場 13:00~13:05 趣旨 13:10~14:00 柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係」 14:05~14:55 岡田泰平「「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」 15:10~16:00 池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録―ビルマ人の場合」 16:05~16:55 師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」 ★ 午前中(10:00~12:00)は、「阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025:東南アジアと戦後80年」の高校生による成果発表がおこなわれます。 応募締め切り 7月24日17:00 登録フォーム(対面) https://forms.gle/XXaN5coJ5D5GAD1T6 登録フォーム(オンライン) https://us02web.zoom.us/meeting/register/jPRaHTWxQGmGgFVvqJi-8Q 連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp 要旨: 柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係―」 タイは開戦当初に日本軍と同盟を結んで枢軸国側に立つことを決意したが、枢軸国側の戦況悪化に伴い、日本との同盟を決意したピブーン首相も日本との距離を取り始める。他方で、タイ国内外で抗日を模索していたグループが連携し、連合国側と協力して抗日蜂起を模索した。この「自由タイ運動」の首謀者であった摂政プリーディーが、日本軍の降伏受諾後直ちに連合軍側への宣戦布告を無効とする「平和宣言」を発表し、「敗戦国」としての扱いを逃れようと画策した。このため、タイにおける第2次世界大戦観は「自由タイ運動」を重視したものであり、日本との同盟の歴史を「負の遺産」と見なすものである。これに対し、当時日本側との連絡役を担っていた職員が作成した同時代資料からは、タイと日本の関係が対等ではなかった点への不満や、自らが日本軍の「手先」と見なされることへの憂慮を読み取ることができ、日タイ同盟の実像の一端を垣間見ることができる。 岡田泰平「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」 この発表では、まずはフィリピン戦における実相を論じ、その上で日比双方の「戦記もの」を読み解いていくことにより、戦争の実相がどのように日比の記憶の中に位置づけられていったのかを確認したい。時が経つにつれて、戦争の記憶は変質していく。1970年代、1980年代になると、すでに時間的にも地理的にも遠くなったフィリピン戦をどのように評価するのかという問題がある一方、フィリピンに慰霊に行く日本人が多くなる。そのような中で、新たな日比の関係が築かれていく。たしかに、フィリピン人の「厚意」(許し)と日本人の「お詫び」という好循環が生じてくるのだが、他方では、新たな日比間の関係を築けない事例も多かった。この発表では、幾つかの事例から、凄惨な経験から生じるものの帰結や同意に達しない関係、つまり「宙ぶらりんの関係」を紹介する。歴史教育の一環として、そしてまた地域研究にとって、そのような「宙ぶらりんな関係」が持つ意義を考えてみたい。 池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録:ビルマ人の場合」 泰緬鉄道は、1943年10月に日本軍がタイ=ビルマ(ミャンマー)間に開通させた軍需物資の輸送鉄道だ。わずか1年4ヶ月の突貫工事で密林地帯を走る415キロを完工できたのは、62,000人の連合軍捕虜と20万を超えるとされる現地労務者の酷使と犠牲があったからであった。戦後、泰緬鉄道の建設が日本軍によるジュネーブ条約に反する戦争犯罪としてひろく世界に知られるようになったが、それは1957年のハリウッド映画「戦場にかける橋」の世界興行と、元捕虜による告発が数多くなされたことによる。日本側では反発とともに永瀬隆氏による贖罪活動が行われた。彼の活動は英蘭豪米の元捕虜との交流と和解の活動にもつながった。こうして「泰緬鉄道」は、日本と欧米において第二次世界大戦史の重要な記憶と記録として定着した。では、現地の人々にとって、それはどのような出来事として記憶され記録されているのだろうか。とくにビルマ人にとっての戦後(独立後)の「泰緬鉄道」を考えてみたい。 師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」 戦後80年を迎えた今も、山下財宝伝説はフィリピン社会に色あせることなく息づく。山下財宝とは、山下奉文大将率いる第十四方面軍がフィリピンに埋めたとされるアジア各国の金銀財宝のことを指す。人々の日常の語りや実践において財宝は、地中に埋もれた遺物として想像されると同時に、未来への可能性を託す地下資源としてもイメージされる。土地に堆積した過去は生活世界の折々に表面化し、財宝の潜在的存在を浮かび上がらせるとともに「あの戦争」や「あの時の日本人」の記憶を確かに呼び起こす。本発表では、こうして反復生成される山下財宝伝説を通じて、正史として記録に残ることのない、残渣としての戦争記憶をいかに人々が共同的・社会的に紡ぎ続けているのかを検討する。 PDF版ポスターはこちら -
小林紀晴監督作品『トオイとマサト』上映会&トークセッション
この度、チェンマイ大学日本研究センターは、国際交流基金の支援を受けて、上映会および監督とのトークセッションを開催いたします。 7月9日(水)1:00-4:00PM@Udon Thani Rajabhat University 7月12日(土)9:00-12:00AM@Chiang Mai University (いずれもタイ現地時間) 詳細は、下記をご参照ください。 - Japanese Studies Center Blog: https://cmujpsc.blogspot.com/2025/06/#8129502319823369069 - Japanese Studies Center Facebook Page: https://www.facebook.com/JapaneseStudiesCenter このドキュメンタリー映画は、写真家・瀬戸正人の自伝エッセイ「トオイと正人」をもとに、写真家・作家である小林紀晴が初めて監督した作品です。ストーリーは、日本軍残留兵の父とベトナム系タイ人の母との間に生まれたトオイは、「正人」として日本で成長していく過程でタイ語を忘れていく、大人になった「正人」は、「トオイ」を探して、タイ、ラオス、福島へと、記憶を辿る旅に出るという内容です。 作品については、https://eiga.com/movie/98786/ 監督については、https://www.kobayashi-kisei.com/ それぞれご参照ください。 国内イベントではありませんが、タイ国における日本研究の現在を知る良い機会かと思いますので、ご案内させていただきます。