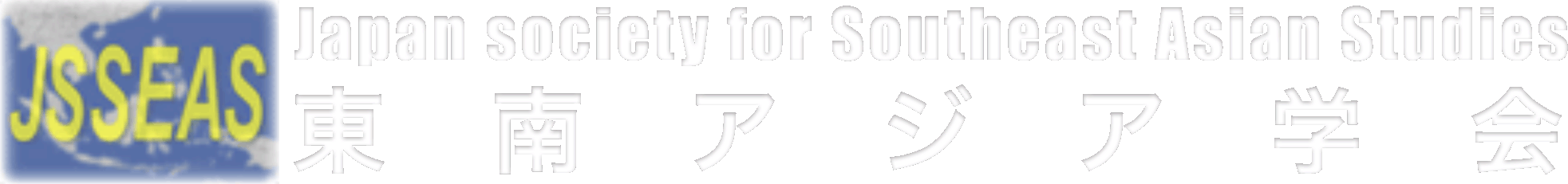東南アジア学会第107回研究大会プログラム
日時: 2025年12月6日(土)・7日(日)
会場: 亜細亜大学 武蔵野キャンパス5号館
開催形態: 対面を重視したハイフレックス形式
(発表者は原則として対面参加をお願いします)
※大会オンライン参加者マニュアル・総会オンライン参加者マニュアル
※プログラム全体のタイムテーブルはこちら
【1日目】 12月6日(土)
9:15 開室
【A会場】511教室(Zoom Room 1)
9:30-9:40 開会の辞: 増原綾子(会場校・亜細亜大学)
パネル1 Two Centuries of Agrarian, Economic, and Ecological Shifts in the North Coast of Java, 1812-2012 (1) Comal- Land Tenure, Rural Stratification, and Sugar Cane Industry[報告要旨]
9:45-11:40 代表: 水野広祐(京都大学/インドネシア大学)
【B会場】526教室(Zoom Room 2)
自由研究発表第1セッション[報告要旨]
司会: 生駒 美樹(東京外国語大学)
10:25-11:00 在日ミャンマー人の民主化運動における非可視的実践と政治的エージェンシー
石川航(立教大学 博士後期課程)
11:05-11:40 マンダレーのメイテイ人社会とヤンゴンのナガ系コミュニティ
村上武則(中央大学 非常勤講師)
【C会場】523教室(Zoom Room 3)
自由研究発表第2セッション[報告要旨]
司会: 渡邉 暁子(文教大学)
10:25-11:00 植民地インドネシアのムスリムが観た第一次世界大戦後の世界: ムハマディヤ系定期刊行物Bintang Islam(1923-1930)を主な資料として
小林寧子(東洋大学 客員研究員)
11:05-11:40 民主化後フィリピンの社会運動における独立活動家: 大統領診断フレームによる大規模動員
瀬名波栄志(京都大学 博士課程)
11:40-12:50 昼食休憩
【A会場】511教室(Zoom Room 1)
パネル2 Two Centuries of Agrarian, Economic, and Ecological Shifts in the North Coast of Java, 1812-2012 (2) Comal- Climate Change, Environment, Society and Economy[報告要旨]
12:50-14:45 代表: 水野広祐(京都大学/インドネシア大学)
【B会場】526教室(Zoom Room 2)
自由研究発表第3セッション[報告要旨]
司会: 福岡 まどか(大阪大学)
12:50-13:25 音楽産業社会への参画と国家的統一からの逸脱: 東北タイ芸能者の事例から
平田晶子(愛知大学)
13:30-14:05 現代シンガポールにおける高齢者演劇の広がり: 高齢者福祉政策と文化芸術政策の転換の交点として
山崎嘉那子(京都大学 博士課程)
14:10-14:45 タイ国安南派仏教における死後世界への関与: 1950-60年代 景福寺住職バーオウーン師の憑依儀礼を中心に
西田昌之(東北学院大学)
【C会場】523教室(Zoom Room 3)
自由研究発表第4セッション[報告要旨]
司会: 菅原 由美(大阪大学)
12:50-13:25 根幹から枯れ枝へ: 東インドネシア、エンデにおける「生命の流れ」の考え方
中川敏(大阪大学 名誉教授)
13:30-14:05 インドネシアにおけるkiṃnara とkiṃnarīについて
伊藤奈保子(広島大学)
14:10-14:45 インドネシアにおける歴史的津波と災害対応の『伝統知』: 中マルク地域を中心に
河野佳春(弓削商船高等専門学校)
【A会場】511教室(Zoom Room 4)
14:50-15:00 受付: 参加者ログイン後、名簿と照会のうえ、入室許可手続き
15:00-16:00 会員総会
【A会場】511教室(Zoom Room 5)
16:10-17:10 OpenSEAライトニングトーク
※報告要旨は「OpenSEAポスター発表」の項参照
- 片山凛、井澤椛(大阪大学 外国語学部フィリピン語専攻 学部生) 現代フィリピンにおける「ポスト・バヤニハン」の思想
- 伊藤雷華(早稲田大学大学院 修士課程) インドネシアの家事労働における仲介者及びその口伝え
の意義:インドネシア中部ジャワ州スマラン市を事例に - 黒沢舞衣(早稲田大学大学院 修士課程) 参加型開発事業終了後の参加者の動向: 東ティモールでの女性事業から考える、意図せざる多様な展開
- 松本咲、豊田侑生、金子喜和、佐藤賢人、田口紗凪(宮
城県仙台二華高等学校2年)アンコールクラウ村でのバイオトイレの導入に向けて:人糞堆肥で 循環型農業 - 伊原来美(東京外国語大学 言語文化学部フィリピン語専攻 学部生) コーヒー生産を通じた若者のコミュニティ開発への参画: フィリピン・コーディリエラとインドネシア・バンドンの比較研究
- 車旺樹、大熊梨花(愛知大学 国際コミュニケーション学部国際教養学科 学部生) 孤食は本当に問題か?タイの若者の声から考える
- 松井深山(広島大学 文学部人文学科 学部生) インドネシアのチャンディ・バノン出土ヒンドゥー教神
像群について - 平山栞菜(広島大学大学院 修士課程) 周縁化された宗教マイノリティにおける共同体想像過程
の研究: フィリピン草創期イスラーム自治地域におけるムスリムを事例に - 内藤愛美(東京外国語大学 国際社会学部フィリピン語科 学部生) アポ山における観光資源と地域開発の可能性: ガイド・ポーターの労働環境とアグロツーリズムを中心に
- 渋谷真由(民間企業、津田塾大学卒業生)東海(南シナ海)領有権問題と中越関係: ベトナム・ハノイ市の若者における問題認識とその形成
17:20-18:50 第23回東南アジア史学会賞授賞式・受賞記念講演
・土屋喜生 会員 Emplacing East Timor: Regime Change and Knowledge Production, 1860-2010 (2024年 University of Hawai‘i Press)
・櫻田智恵 会員 『国王奉迎のタイ現代史: プーミポンの行幸とその映画』(2023年 ミネルヴァ書房)
19:00-20:20 懇親会 アジアプラザ(学生食堂)4階
【2日目】 12月7日(日)
9:30 開室
【A会場】511教室(Zoom Room 1)
パネル3 グローバル時代におけるハラール基準の標準化と多様性の動態[報告要旨]
10:00-11:55 代表: 大形里美(九州国際大学)
【B会場】526教室(Zoom Room 2)
パネル4 カンボジア・タイ領土紛争の政治[報告要旨]
10:00-11:55 代表: 玉田芳史(放送大学)
11:55-13:00 昼食休憩
【A会場】511教室(Zoom Room 5)
12:45 開室(一般公開)
13:00-17:00 大会シンポジウム「東南アジアの国民国家を問い直す」[報告要旨]
(共催: 亜細亜大学アジア研究所市民講座「アジアウォッチャー」)
- 趣旨説明: 増原綾子(亜細亜大学)
- 片岡樹(京都大学) 東南アジア国家はどの程度東南アジア的なのか?
- 池田一人(大阪大学) ビルマ・ナショナリズム/国民国家論の再考
- 大泉啓一郎(亜細亜大学) 東南アジアの福祉国家と国民国家
- 討論: 左右田直規(東京外国語大学)
- 討論: 佐々木拓雄(久留米大学)
17:00-17:10 閉会の辞: 小林知(東南アジア学会会長・京都大学)
【ポスター会場】5号館1階
OpenSEAポスター発表[報告要旨]
- 鈴木雅斗(元市川市議会議員) 戦時下に分裂したインディアン銀行、日本軍統治下マラ
ヤと英領インドにおける2つのインディアン銀行と日本軍政下の銀 行活動の証明にむけて - 洲脇聖哉(監査法人 米国公認会計士) 国際関係論の欧米史偏重を超えて: 東南アジア史の視点から
- 村田友司(法政大学大学院 後期博士課程) 「福祉の複合体」による森林環境管理と農民のWell-beingの考察: インドネシア・スマトラ島フィールドワークから見る製紙会社の役割
- 渋谷真由(民間企業、津田塾大学卒業生) 東海(南シナ海)領有権問題と中越関係: ベトナム・ハノイ市の若者における問題認識とその形成
- 車旺樹、大熊梨花(愛知大学 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 学部生) 孤食は本当に問題か?タイの若者の声から考える
- 木戸美花・梶田百花(愛知大学国際コミュニケーション
学部国際教養学科)信仰と環境保護 : タイにおける仏教・アニミズム・伝統の交差点 - 木谷公哉(京都大学 東南アジア地域研究研究所 助教) 東南アジア研究における学術誌の役割と活用状況
- 内藤咲愛(横浜国際高等学校) マラヤ非常事態でのマラヤ独立のプロセスにおけるイギリスの影響と冷戦の様相
- 片山凛、井澤椛(大阪大学 外国語学部 フィリピン語専攻 学部生) 現代フィリピンにおける 「ポスト・バヤニハン 」の思想
- 松井深山(広島大学 文学部人文学科 学部生) インドネシアのチャンディ・バノン出土ヒンドゥー教神
像群について - 帯金蒼人、小沢志生、三輪 純正、古茂田遥太、大澤司(成城高等学校普通科)カンボジア農村調査に於ける現地の農村の現状とその未来
- 岩木祥哉・白井りの・五十嵐琴珀、荒引心温、荻原紗季
(上田高校カンボジア井戸プロジェクト) 「カンボジア井戸プロジェクト: カンボジアに井戸を贈る」 - 清水英里(亜細亜大学、大東文化大学、東京外国語大学オープンアカデミー 非常勤講師) ベトナム語学習における「手書き」と「タイピング書字」の違いとその効果
- 黒沢舞衣(早稲田大学大学院 修士課程) 参加型開発事業終了後の参加者の動向: 東ティモールでの女性事業から考える、意図せざる多様な展開
- 内田陽向、嵯峨悠月、丸山美智、渡辺絢葉(仙台二華高等学校) カンボジアの学校菜園の現状と課題
- 松本咲、豊田侑生、金子喜和、佐藤賢人、田口紗凪(宮
城県仙台二華高等学校2年) アンコールクラウ村でのバイオトイレの導入に向けて:人糞堆肥で 循環型農業 - 和久田彩世(仙台二華高等学校) バイヨン中学校・高等学校の生徒の睡眠の質と学力の関係性
- 大庭フランシス光瑠(広島大学大学院 博士課程) ポスト・トゥルース時代の社会運動における草の根親密
圏とデジタル公共圏のあり方: 2025年インドネシアの全国規模なデモを事例に - 内藤愛美(東京外国語大学 国際社会学部 フィリピン語科 学部生) アポ山における観光資源と地域開発の可能性: ガイド・ポーターの労働環境とアグロツーリズムを中心に
- 伊原来美(東京外国語大学 言語文化学部 フィリピン語専攻 学部生) コーヒー生産を通じた若者のコミュニティ開発への参画: フィリピン・コーディリエラとインドネシア・バンドンの比較研究
- 伊藤雷華(早稲田大学大学院 修士課程) インドネシアの家事労働における仲介者及びその口伝え
の意義:インドネシア中部ジャワ州スマラン市を事例に - 小林磨理恵(アジア経済研究所 図書館司書) タイ国王の理想化と記念化: ラーマ9世葬式本の分析
- 山田晃輔、相崎開(成城高等学校)カンボジアのサッカーチームの経営改善へ向けたポスター発表